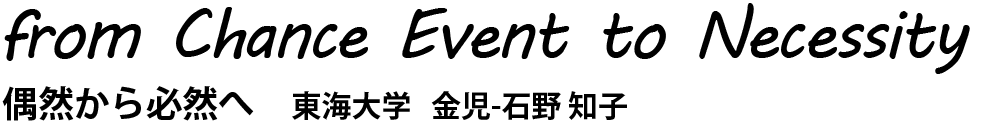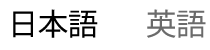金児-石野 知子
東京大学大学院理学系研究科生物化学専攻 博士課程修了 (理学博士)
Tomoko Kaneko-Ishino Ph.D.
1991年に留学先 イギリスのアジム・スラーニー研究室から、分与された雌性単為発生胚サンプルを持って帰国、東京工業大学においてインプリント遺伝子のスクリーニングを開始した。共同研究者 石野史敏と開発したサブトラクション法を用いて、当初のスクリーニングで得られたインプリント遺伝子は既知の遺伝子(Peg3を除く)で、予想していたウイルスなどの外来DNAに由来する遺伝子は見つからなかった。その後、助教授として東海大学に移り、スクリーニングしたインプリント遺伝子がすべて胎盤で発現しているという仮説を東工大の学生とin situ hybridizationで確認できたときは、自分の考えの方向が間違っていないと思えてうれしかったことを覚えている。
当初から私の目的はインプリント遺伝子の中にウイルス由来の哺乳類特異的獲得遺伝子を見つけることで、インプリンティングという哺乳類に特異的な機構を通したアプローチが有効であると考えていた。しかも、イギリス留学中の1990年にH19遺伝子というインプリント遺伝子が獲得遺伝子候補であることに気づいていたので、多数見つかってくるだろうと思っていた。しかし、獲得遺伝子であるPeg10、Peg11に出会えたのは10年後の2000年であり、予想よりはるかに少なかった(Headline 2 参照)。
そのころには、インプリント遺伝子がクラスターをなし、インプリント領域を作っていること、領域には必ず父親・母親由来のゲノムでメチル化の差があるDMRが存在することもわかってきたため、個々のインプリント遺伝子ではなく、DMRこそが外来由来のDNAであると仮説を修正し、オーストラリア、東京医科歯科大学(東工大から共同研究者の石野が異動)との共同研究で証明できた(Headline 3参照)。
その後、東京医科歯科大学との共同研究でPeg10、Peg11と同じく、Gag proteinと相同性をもつ9個の哺乳類特異的獲得遺伝子を見出し、この11個をSirh familyと名付けた。Peg10、Peg11はKOマウスが胎仔期致死になるため、遺伝子機能が胎盤にあるとの目安がまだつけやすかった(Headline 4,5参照)。
残りのSirh遺伝子になると、胎盤の内分泌機能や脳機能(KOマウスが固有の行動異常を示す)など、直接、生死に関わるものではなく、生命機能のよりよいアレンジに関わる様相を呈してきて、解析がどんどん難しくなっていった。
しかし、哺乳類特異的獲得遺伝子として哺乳類に広く保存されていることには、哺乳類にとって必ず意味があると信じて、解析を進めてきた。
現在、Peg10、Peg11に加えて胎盤機能ではSirh7(スピンオフ1)、行動異常を示すSirh11(スピンオフ2)、Sirh3まではある程度その意味が理解できたと思えている。残りのSirh8(行動異常を示す)、Sirh4,5,6はヒントが得られたところ、Sirh9はKO観察中、ずっと気になりながら最後になったSirh10、いずれも哺乳類のみに存在し、Sirh family同士でしか相同性がなく、どれも既存の遺伝子から機能を類推することができない。
今までの研究者人生で培った知識・経験と感(“感”とはあてずっぽうではなく“言語化されていない思考”だと私は考えている)のすべてを駆使して、これらの遺伝子を理解しようと努めている。それでも、しょっちゅう熟考の裏をかかれるような結果が出て、やられたと思う。ほんとうに手強い。だからこそ、このSirh familyにはまったのかも知れない。
研究生活の中で出会って、一緒に研究を進めた大学院生やポスドクの皆さん、共同研究を行った国内外の研究者の方々、研究を直接・間接に応援してくださった方々、
この研究に関わって下さったすべての方に感謝します。
ポスドク時代に時間をかけて考えた研究テーマを幹として、30年間楽しみながら育て、発展させて来られたことは、とても幸せなことだと感じています。
ここまでは2020年3月に記した「あとがき」である。当時は、Sirh4 ,5, 6は脳での発現やDKOマウスの行動異常から機能に迫れる見込みがつきはじめていた(ヘッドライン8参照)。しかし、ノックアウトマウスでほとんど表現型が見られなかった遺伝子群に関しては、遺伝子がない方から迫るという定法通りのやり方では、ほんとうの機能に迫れないと判断し、蛍光タンパク質を融合したノックインマウスで遺伝子の機能を追うことに研究をシフトしていた。
Sirh3-Venus、Sirh8-mCherry、 Sirh10-mCherry、Sirh11-Venusと次々にノックインマウスを作製しながら、まずSIRH3-Venusタンパク質の挙動を共焦点レーザー蛍光顕微鏡で追う日々だった。ノックインマウスの解析を進めるとVenus、mCherryともに自家蛍光との重なりがあり、いかにきれいに自家蛍光と分けるかが重要であった。発現量が多くない(それが自然な発現量なのだが)タンパク質を解析する場合に、自家蛍光を除いた蛍光シグナルだけを追う必要があるが、そのような解析ができるのはZeiss LSM880 (LSM880)だけだった。ようやく2017年12月に東海大学の生命科学統合支援センターに導入してもらえたおかげで、研究を進めることができたのである。
遺伝子発現量の多い脳でSIRH3-Venusの蛍光を追ってみたが、シグナルの検出はできるようになったものの、なかなか解析の方向性が定まらない。脳内のシグナル分布を解析しても、毎回の解析で少しずつ違って見えたりして発現場所を詰め切れない。この試行錯誤の繰り返しでかなりの時間使ってしまった。
2021年2月16日、共同研究者が細心の注意を払ってノックインマウスを解剖し、私も完璧によい状態だと思えた脳サンプルを期待に満ちてLSM880で解析を行った。その結果はそれまでのどのサンプルよりもシグナルが低かった、いやむしろシグナルがなかった。その時気が付いた。一生懸命よい状態の脳を採取しようとしたのは方向が間違っていた、SIRH3-Venusはむしろ脳のダメージによって活性化するのだろう、と。そして自然界でのダメージといったら一番怖いのは感染症だろう、と。感染源に細菌やウイルスを想定して、すぐに蛍光のついたLPS(細菌感染を模倣)を購入してノックインマウスの脳に加えて解析したところ、SIRH3-Venusタンパク質がLPSに結合する画像が見えた。これが正しい方向性だったのである。SIRH3タンパクは脳特異的な免疫細胞であるミクログリアで発現し、脳内に存在して感染時に細菌と結合し、除去しやすくする働きをしていることがわかった。
それからは一本道だった。Sirh8遺伝子もミクログリアで発現し、ウイルス感染を模したdsRNAにSIRH8-mCherryが反応した。自然界でカビの感染も侮れないと考え、カビを模したザイモサンを用いたところSIRH10-mCherryが反応した。つまり、Sirh3, Sirh8, Sirh10はいずれもミクログリアで発現し、いろいろな感染源に反応してその除去に関わる自然免疫のフロントラインだったのである。
SIRH11-Venusは自然免疫ではなくノルアドレナリン(NA)と反応した。NAは重要な神経伝達物質であるが細胞毒性もある。そのため、SIRH11タンパクがすばやく結合して再回収を助け、細胞へのダメージを抑えているのではないかと考える。
つまり、Sirh3、 Sirh8、 Sirh10、Sirh11はいずれも脳を護る戦士たちだった、ということだろう(ヘッドライン9参照)。
2021年2月16日の観察から一気に道が開け、次々とSIRH/RTLタンパク質の機能を解明できたことはうれしい限りである。あの日の「Eureka!」という感覚は忘れられない。
2025年3月
東海大学医学部看護学科
〒259-1193
神奈川県伊勢原市下糟屋143
TEL: 0463-93-2111
e-mail:tkanekoi@tokai.ac.jp